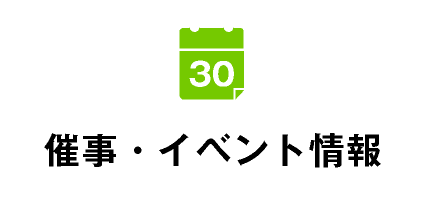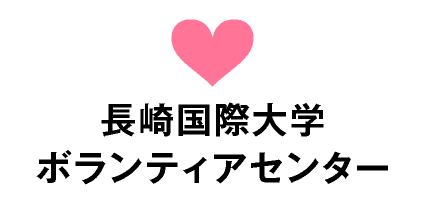カリキュラム・シラバス
「講義概要(シラバス)」を読む前に
この「講義概要(シラバス)」は、事前・事後に必要な学修事項を確認し、自主的・意欲的に授業に臨んでいただくために、作られた学修上のガイドブックです。
先生方が担当されるそれぞれの科目について授業の概要や進め方を示していますので、皆さんはそれを読んで科目の選択の参考にするとともに、問題意識を持ち、意欲的に授業に臨み、学修上有意義な4年間もしくは6年間を送ってください。
「講義概要(シラバス)」は、つぎのような内容で構成されています。
授業のねらい
前期又は後期開講科目の15回の授業(場合によっては増減することもあります)、通年開講科目30回の授業を通じて修得できる知識やスキルを各学科の教育目標を踏まえて明示しているので、学修の意義を理解することができます。
学生の授業における到達目標、評価手段・方法、評価比率
各授業において、学生の皆さんが「何を学び」、「何が出来るようになるか」、科目の行動目標を明示するとともに授業終了時の到達目標を観点別に具体的に記載しています。また、当該科目における到達目標に達成したかどうかを判定する方法と評価基準、複数の評価方法を使用する場合の配分割合を記載しています。
評価基準及び評価手段・方法の補足説明
各授業における成績評価の基準を具体的に記載したもので、試験、小テストの実施日、レポートの提出等を記載していますので、計画的に学修していくように心掛けてください。
なお、学修の評価は原則として100点法で行います。授業担当者から個別に評価基準が示されていない場合は、本学の基準に照らし合わせて行います。
| 評価 | 評点 | 評価基準 | |
|---|---|---|---|
| 合格 | S | 100~90点 | 到達目標を十分達成し、きわめて優秀な成績を修めている。 |
| A | 89~80点 | 到達目標を十分に達成している。 | |
| B | 79~70点 | 到達目標を達成している。 | |
| C | 69~60点 | 到達目標を最低限達成している。 | |
| 不合格 | D | 59点以下 | 到達目標を達成していない。 |
| F | 出席不良等 | 出席・試験(レポート等の提出)の評価要件を欠格。 | |
※上記の成績評価とは別に「成績通知書」に次のように標記されるものがあります。
- 編入による入学前の既修得単位の認定、技能審査による単位認定及び留学に伴う単位認定等:Q
- 履修登録辞退制度により指定された期間に履修登録を辞退した科目:G
授業の概要
授業の全体を把握できるように授業で扱う主なトピックに係るキーワードを使用し、次頁の授業内容の理解を助けます。また、授業外学修時間を記載しています。2単位90分の授業であれば90分の予習と90分の復習が必要となります。演習、実習等では授業外学修の時間が異なりますので、担当教員の説明をよく聞いて、「予習」⇒「授業」⇒「復習」のサイクルを維持しながら授業を受けてください。
教科書・参考書
教科書は、授業を進める場合の基本となるものですので、必ず購入するようにしてください。
参考書は、自主的に学習を進めていくうえでの参考となるものです。また、「100冊読書」にカウントされる1冊を記載しています。書物からの学びによって、静かに考え、一歩先を読む態度を育成することが、変化の激しい社会の中にあって、人間性をより豊かにすると考えています。
授業外における学修及び学生に期待すること
1単位の修得に必要な時間は45時間(講義の場合は受講15時間と予習・復習に30時間)となっているため、大学は、「授業1時間に対して予習・復習2時間」という考えのもと、授業外(予習・復習)における学修方法・内容について記載しています。
また、担当者から学生に期待すること、受講の心構え等についても示しています。
テーマ、授業の内容、予習・復習
授業毎のテーマ、そのテーマの具体的な内容及び予習・復習の内容について、授業時間を追って記載しています。よく読んで「予習」、「復習」を行ってください。授業について質問がある場合は、「リフレクションカード」や「オフィスアワー」を利用してください。授業内においてもフィードバックを行います。
また、ポートフォリオを通して各回の授業に関するお知らせや課題(小テストやレポート)の通知・結果のフィードバックを行います。課題やレポート作成のため調べた内容も含めて、随時、ポートフォリオに保存されます。学生の皆さんは、先生方からポートフォリオに新しいお知らせや書き込みがあった場合確認できるようリマインダ設定をします。
オフィスアワーについて
本学では、皆さんの授業の質問や学生生活全般にわたる相談に応じるため、オフィスアワーを設けています。オフィスアワーは学生が先生と直接に接触し、専門の研究分野はもちろんのこと、学業や学生生活上の諸問題等いろいろな相談事について、適切な助言を得るための時間です。学生にとって、もっとも大切な学修研究と人間形成に役立つものです。在室の日時を設定していますので、積極的に、また、気軽に研究室等を訪ねるようにしてください。
このシラバスを最大限利用して、実りある学生生活を実現してください。
アクティブ・ラーニングについて
本学の全授業において、
アクティブ・ラーニングを取り入れ展開します。
本学の全授業において、アクティブ・ラーニングを取り入れ展開します。
「アクティブ・ラーニング」を日本語にすると「能動的学習」と訳します。つまり、学ぶ姿勢や態度が受動的ではなく能動的だということです。
授業は一方的な知識伝達型になりがちです。先生が一方的に講義をし、板書されたものをノートにとるだけだと受動的に学んでいるので、理解も深まらず知識も定着しないことがあります。また、この授業スタイルだと「思考力」や「判断力」、「表現力」などは育ちにくいのが実情です。そこで、学生の皆さんがいかに能動的に授業に参加するかという工夫が必要になるのです。このことを踏まえ、本学では、全授業においてアクティブ・ラーニングを取り入れます。
これから皆さんは、次の①~⑫のアクティブ・ラーニングが取り入れられた授業を受講するようになります。どの形式に沿って授業が行われるか事前に確認し、「予習」⇒「授業」⇒「復習」のサイクルを維持しながら授業を受けてください。
また、なぜ、大学の授業においてアクティブ・ラーニングが必要かと思っている人もいるかもしれません。それは、今後の日本の社会で起きている大きな変化である、“少子高齢化”、“グローバル化”、“高度情報化”という3つのことが大きな課題となっていることです。
本学のディプロマ・ポリシーにおいてホスピタリティを構成する5つ諸能力である「専門力」や「情報収集・分析力」、「コミュニケーション力」、「協働・課題解決力」、「多様性理解力」を身に付けることで、これから皆さんが社会に出たときに協働して問題を解決したり、自分自身で新しいことを創造する力で、それぞれの専門分野から3つの課題を克服することができると考えます。これからの変化の激しい社会を迎えるにあたり一緒に頑張っていきましょう。
アクティブ・ラーニングの類型
シラバスの「アクティブ・ラーニングの類型」欄に授業で取り入れるアクティブ・ラーニングの番号を記載しています。どの形式に沿って授業が行われるか事前に確認して下さい。
- 予習を課し、それをもとにした授業
- 授業の導入段階で授業テーマに学修者が興味・関心を持つように工夫する授業
- 授業の終末段階で次時の授業に学修者が興味・関心を持つように工夫する授業
- 学修者個人やグループに課題解決を促す授業(PBL等)
- ある課題について議論を促し、ディベート等を行う授業
- ある課題について調査した結果を個人やグループで発表させる授業
- ある体験を課し、その中で感じたことをもとに議論したり、発表させる授業
- 次時の学修内容を課題にして、事前に取り組ませ、課題の解説や解答を中心とする授業
- 学期途中で小テストを課し、学修者の省察を引き出し能動的な学修を喚起する授業
- 学期途中で課題をだし、レポートを纏めることによって能動的な学修を喚起する授業
- 既修事項をもとにした能動的な活動を行う授業
- 自己の課題を挙げ、その解決に取り組む授業
①~⑫の形態を単独或いは複数組み合わせた授業展開を行うことによって、学修者の主体性を引き出し、学修を自分にとって意義あるものと認識させた上で、能動的に授業への参加を促すものとする。