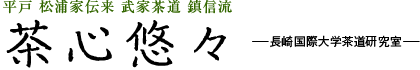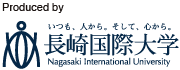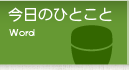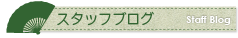2025年07月17日
第5回「波佐見茶会を終えて・・・」
茶道文化Ⅳの集大成としての茶会が、7月5日波佐見町の歴史的な場所、「波佐見町歴史博物館」で開催されました。学生の皆さんにとっても、学びの成果を地域と共有できる素晴らしい機会になりました。
今回は、お客様の申し込みが多く、どの席も満席。お客様には、茶席の時間を待つ間、木々の揺らぎと空間を味わい、館内の展示物も見ていただきました。
さて・・・ようやくお待たせのお茶席です。
茶席は、薄茶点前の逆勝手。今回のテーマは、七夕のロマンチックな雰囲気と水の清らかさや涼しさを表現してみました。水指に笹の葉の絵、棗には蛍の笹の水、平茶碗の底に花びらの形どったものなどを用意し、幻想的なイメージが広がってほしいと願いを込めました。
そして亭主は、たくさんの練習を重ね点前を披露いたしました。緊張感と達成感が満ち溢れる時間でした。半東さんは、お客様からの多くの質問に、一生懸命答えていた姿が誇らしく感じました。




水屋は、まずは美味しいお茶を点てることに専念しました。授業の際でも何度もお茶を点てて、お湯の温度、抹茶の量などを調整しました。


そのお茶をお客様に届けるのが接待の役目でもあります。茶室が狭いのでその狭さをお客様に感じさせないように、1人の人が座ってお茶を出せるように工夫をしました。




受付は、待っているお客様の対応や人数などを水屋に伝え、一般客や卒業生、学園内のお客様の対応に追われました。お子様ずれのお客様や座ることができないお客様に対しての配慮にも心掛けるなど、人対人の関係の学びを沢山致しました。
それぞれの役割のなかで、実践を通して学ぶことの意義や連帯感の大切さ、さらには人や物に対する優しさも学ぶ良い機会となりました。
主催した学生の感想
亭主としてお点前をする中で、一つ一つの小さな動作に集中し、そのすべてが正客をはじめとしたお客様へのおもてなしであることを意識した結果、客と亭主、お茶会全体に一体感があった。半東が緊張から言葉に詰まることがあり、もう少し客と半東とのやり取りの練習をしておくべきだったと思った。(国際観光学科4年)
練習通りにいかない部分もあったが、接待間での取り次ぎの練習の成果を発揮できた茶会にすることができ良かった。接待という役割を通して、接待は、亭主、半東、水屋全ての役割と繋がっている部分があり、接待の動きができていないと茶会を上手く動かせないと感じた。(国際観光学科4年)
本番での反省点は、想定外の流れに戸惑うことがあり、自分で考えて行動できていない部分があったことである。しかし、その中でもお客様に対して丁寧に対応することができた部分は良かったと思う。(国際観光学科4年)
自分の役割をこなしながらも、しっかりチームの一員として周りを見て、時には他のポジションにも気を配る大切さを将来に役立てていきたい。また、おもてなしの心も忘れない。(国際観光学科4年)
フィールドワークとしてお茶会に参加した学生の感想
今回参加させていただいた波佐見茶会が人生で初めての茶会だったので、とても緊張していたのですが、私が想像していたよりもはるかに優しい雰囲気と柔らかい雰囲気があり、緊張していたのですが安心して茶会に参加することができました。(国際観光学科1年)
少し難しかったけど授業などでは体験することのないことをことなので体験する事が出来てよかったです。また、今日の掛け軸が「平常心是道」というものでした。先輩方が今までやってきたことを発揮するという意味だと伝えられました。掛け軸にもお茶会に対しての意味がありどんな理由で掛けられているのか知ることができました。(国際観光学科1年)
お手前だけではなくて、お茶を運ぶところもヘリを踏まずにすり足で歩くまた、お茶を立って一人一人回るのではなく、バトン渡しのようにほこりが立たないようにお客さんに提供していることを学びました。(国際観光学科1年)
そして「もてなし」とは何なのか?
茶の湯の静けさや精神性。展示物と学生の立ち居振る舞い。亭主と客の関連性など。響き合って、まるで時代を越えた文化交流のように思えます。
これから、学生たちは卒業茶会を目指して「一期一会」の精神で頑張ってほしいと願っています。