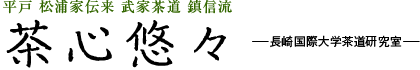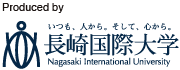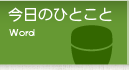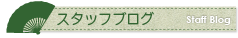2025年07月01日
「茶道文化ⅢA」グループでの実技試験
「茶道文化Ⅲ(3年次開講科目)」を履修している学生は、「茶道文化Ⅳ(4年次開講科目)」への履修を目指すに当たって、「茶道文化Ⅰ(1年次必修科目)」と「茶道文化Ⅱ(2年次開講科目)」で点前の基本である、「薄茶点前」と「濃茶点前」を学んでいます。
今回、それらの点前が、お客様を迎える茶会の中で、どのような組み立てになっているのかを確認することを目標にグループでの実技試験を実施しました。グループでの実技試験の内容としては、亭主、半東、客といった茶会での役割に分かれて、それぞれの作法等の理解度を実践を通して確認するというものです。実技試験に向けて、授業の中でも各役割に分かれて、練習を行いました。


試験内容:茶会における薄茶の場面を想定して試験を実施。
実施方法:授業で学んだことを基本にして、4名で1グループを作り、学生は亭主、半東、客の3つの役割から実践内容を選び、試験に臨む。
亭主は、前半(お茶を点てて客に出す)と後半(茶碗が戻り仕舞うまで)に分けて、2人態勢で薄茶の点前をするという形式をとり、点前が基本通りにできているかを確認しました。
半東は、菓子器を運ぶ作法、お茶を出す作法等ができているかどうか、また、その際の給仕口の出入りについて理解できているのかを確認しました。
客は、出入り口の入り方、襖の開け閉め、席入りができているのか、お菓子を取るタイミングと取り方、お茶の飲み方、亭主への声掛けなどを確認しました。




今回のグループでの実技試験を実施した結果、学生の茶道に対する意識が向上したことや、自分の役割を真剣に、そして真摯に受け止め実践したこと、茶会の流れである亭主と客(迎えるものと迎えられるもの)との関係性が理解できたのではないかと考えられます。
ここで、実際にグループテストを受験した学生のコメントをいくつか抜粋して掲載します。
今回はグループでのテストということで、次客にお茶を出したときに正客がお茶を飲み終えている状態だったかを確認したりと、常にグループの他の担当の人がどのような状態だったのかを周りを見て考えて動くことが出来たと感じる。これは茶道だけに言えることではなく日常の生活や、部活動などでも役立てることができる部分だし、茶道を通してこのように日常に役立つことも学習することが出来るというのはとてもプラスなことだなと感じることができた。(国際観光学科 Nさん)
グループでしたおかげで、みんなとコミュニケーションがとれ、関わることのない違う学部の人ともお話しして仲良くなることができた。1人では気づけなかったことも、みんなの意見を聞くことで理解することができた。また、茶道で大切にされている「おもてなしの心」や「思いやり」が、実際の協力の中でも感じられた。反省点もあるが、グループで一つのことに取り組む楽しさと達成感を味わえた、貴重な経験になった。(国際観光学科 Fさん)
これから「茶道文化Ⅲ」を履修している学生は、後期に「錦秋茶会」を実施いたします。この茶会は、大寄せの茶会で100名という大勢のお客様を一同にお迎えして開催する茶会です。
学生にとって、それぞれの役割を学ぶことで「おもてなし」とは何か?について考える機会を今後も与えていきたいと思います。