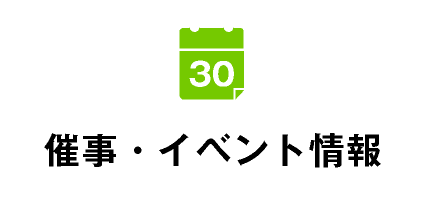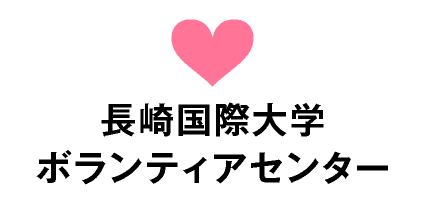「福祉」といえば高齢者や障害者をイメージしがちですが、「児童」を対象とした福祉にも累々とした歴史があります。社会福祉学科の「今」を伝えるべく、豊島律教授による「児童福祉論」に潜入してきました。
 受講するのは社会福祉学科1年生と2年生、合同での講義です。「子どもの置かれている現状は日々刻々と変化しつつあり、また子どもをめぐる問題にはその時代性が刻印されている」という豊島教授。その時代性を見落とさないよう、講義では毎回はじめに新聞記事が配られ、それについて先生が解説をされます。講義は「子どもの成長・発達を阻害する要因や社会的背景を考えること」「問題を捉える力を涵養すること」を念頭において進められ、用語の単なる暗記ではなく、その言葉を歴史的・社会的文脈に位置づけて理解できるよう丁寧に解説をされます。この日のテーマは「子ども家庭福祉とは何か、及び児童福祉の発達について」。内容は子どもの権利、親権、子どもの福祉と多岐にわたりますが、ひとつひとつを噛み砕いて歴史・理念・条文を分かりやすく説明されます。懇篤で品位ある語り口が特徴の"豊島節"に思わず引き込まれていく学生たち。気づけば彼ら・彼女らは「児童福祉」を通じて社会のあり方、ひいては人の生き方を根底的に考えさせられます。
受講するのは社会福祉学科1年生と2年生、合同での講義です。「子どもの置かれている現状は日々刻々と変化しつつあり、また子どもをめぐる問題にはその時代性が刻印されている」という豊島教授。その時代性を見落とさないよう、講義では毎回はじめに新聞記事が配られ、それについて先生が解説をされます。講義は「子どもの成長・発達を阻害する要因や社会的背景を考えること」「問題を捉える力を涵養すること」を念頭において進められ、用語の単なる暗記ではなく、その言葉を歴史的・社会的文脈に位置づけて理解できるよう丁寧に解説をされます。この日のテーマは「子ども家庭福祉とは何か、及び児童福祉の発達について」。内容は子どもの権利、親権、子どもの福祉と多岐にわたりますが、ひとつひとつを噛み砕いて歴史・理念・条文を分かりやすく説明されます。懇篤で品位ある語り口が特徴の"豊島節"に思わず引き込まれていく学生たち。気づけば彼ら・彼女らは「児童福祉」を通じて社会のあり方、ひいては人の生き方を根底的に考えさせられます。
 子どもを取り巻く社会環境が複雑さを増すなか、多種多様な問題が取りざたされています。「児童福祉論」にて「児童」という存在を福祉的観点から考える力を養った学生たちは、児童相談所職員、スクール・ソーシャルワーカーなど、卒業後は児童福祉の現場で専門家としての活躍が期待されます。福祉の究極的目標が人々の幸福にあるとするならば、子どもの幸せは未来社会の財産に直結します。高校生・他分野で学ぶ大学生・社会人の皆さんも「児童福祉論」で子どもと福祉の最前線を学んでみませんか。
子どもを取り巻く社会環境が複雑さを増すなか、多種多様な問題が取りざたされています。「児童福祉論」にて「児童」という存在を福祉的観点から考える力を養った学生たちは、児童相談所職員、スクール・ソーシャルワーカーなど、卒業後は児童福祉の現場で専門家としての活躍が期待されます。福祉の究極的目標が人々の幸福にあるとするならば、子どもの幸せは未来社会の財産に直結します。高校生・他分野で学ぶ大学生・社会人の皆さんも「児童福祉論」で子どもと福祉の最前線を学んでみませんか。
豊島律教授「今日、子どもたちはどのような生活実態の中にいるのでしょうか。また、子どもたちの生活基盤である家庭はどのような状況の中にあるのでしょうか。児童福祉論では、まず、子どもたちが置かれている生活実態(たとえば、子どもの虐待件数がここ20年ほどの間に36倍に増加していること、など)を知っていくことから始めます。
そして、そうした状況の背景を探り、また、その状況ゆえに抱えさせられがちな困難に対して、どのような支援が必要かについて考えていきます。」
学生から
 毎回新聞記事を取り上げて下さるので、身近な話題から児童福祉を学んでいくことができます。最新の動向、ホットなニュース、心揺さぶられる記事などがありとても為になります。 (大浦幸子・社会福祉学科2年)
毎回新聞記事を取り上げて下さるので、身近な話題から児童福祉を学んでいくことができます。最新の動向、ホットなニュース、心揺さぶられる記事などがありとても為になります。 (大浦幸子・社会福祉学科2年)
 先生は経験がとても豊富な方で、保育園での経験談など、具体例を交えながら教えて下さるので、聞いていて思わず引き込まれます。(吉用充紀子・社会福祉学科1年)
先生は経験がとても豊富な方で、保育園での経験談など、具体例を交えながら教えて下さるので、聞いていて思わず引き込まれます。(吉用充紀子・社会福祉学科1年)
「子供」という言葉の字義自体から説明くださり、ついつい見逃しがちな原義を根源的に知ることができます。 (福崎麟太郎・社会福祉学科1年)
配布される資料が豊富ですが、系統立ててお話くださるので情報洪水になることなくノートも取りやすいです。将来は児童福祉関係の職に就きたいのでこの講義はとても勉強になります。(山崎千尋・社会福祉学科1年)