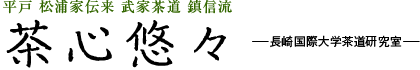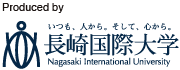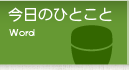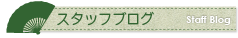2019年11月12日
開国祭 茶道部茶席
長崎国際大学では、11月2日(土)、3日(日)に開国祭が開催されました。濃茶席と立礼席の2席を茶道部の3年生から1年生が力を合わせて、おもてなしをいたしました。
今年の茶道部のテーマは「初心」。令和の時代が幕を開け、新たな気持ちで臨みたいという学生の思いが込められています。
濃茶席の待合に、『阿蘭陀船絵巻』の塗盆を、飾りました。平戸のオランダ商館、長崎の出島に縁のある阿蘭陀船が描かれており、さらに元号が改まり、長崎国際大学と茶道部の新たな時代への「船出」の意味を込めております。濃茶席は、長板の点前を行いました。学生は緊張した面持ちでしたが、お客様から優しくお声かけをいただく場面もあり、心温まる経験ができました。
 ああ
ああ
ああああ濃茶席 接待の様子
薄茶席では、1、2年生を中心に立礼の席でのおもてなしをいたしました。初めてお点前をする学生もおり、不安もあったようですが、お客様との関わりを通して、もてなすことの大切さを学ぶ良い機会となりました。


ああああ薄茶席 接待の様子
夏季休暇期間中に練習を重ねてまいりました。茶会が終えると学生達は達成感を感じ、とても安堵した様子が印象的でした。学生たちは、「臨機応変に対応することの大切さ」や「お客様に喜んでいただきたいという心の在り様」などを学ぶことができたと言っておりました。
今後も鎮信流の教えを学び、大学茶道部としての伝統を、後輩たちに受け継いでほしいと願っております。
2018年02月27日
長崎日本語学院茶道体験
日 時:2018年1月25日(木)10:00~11:30
場 所:長崎国際大学 茶室「自明堂」
主 旨:長崎日本語学院が留学生の日本文化理解の一環として開催している行事で、今年で5回目となります。本学の学生と教職員が、長崎日本語学院の皆さんに日本文化の一つである茶道文化を理解していただくために、薄茶や濃茶の点て方 体験や浴衣の着付け体験をすることが目的となっています。この茶道体験で本学のホスピタリティ精神に触れ、茶道の魅力について感じてもらいたいと思います。
参加者:長崎日本語学院の学生30名(茶道体験サポート学生3名)
1.茶道体験
ここでは、お茶の飲み方とお菓子の取り方を体験してもらいました。
補助員として、本学で茶道文化の授業をサポートしている学生に手伝ってもらいました。
授業とは違った雰囲気の中でも茶道の知識をしっかりと留学生に伝えようと、積極的にコミュニケーションをはかっていました。

さて、お菓子の取り方では、相客のことを考え「お先に」と声をかけてからお菓子を取ります。
お茶の飲み方では、武家茶である鎮信流の作法に沿ってお茶碗を回さない飲み方を学んでもらいました。また、今回は薄茶だけではなく、濃茶にも挑戦してもらい「お茶にも2つの種類があるんだ」と留学生は驚いていました。


2.着付け体験
着付けの体験をする学生は男性と女性に分かれ、帯の締め方や袴の着方など、普段の生活の中ではなかなか体験することのできない動きに挑戦してもらいました。
慣れない動きに苦戦する留学生。
本学のサポート学生に手伝ってもらいながら、綺麗に着付けをすることができました。

わずかな時間ではありましたが、茶道文化体験を通して「日本文化」「茶道文化」を感じてもらえたのではないでしょうか。
ぜひ、茶道だけでなく様々な日本文化にも興味を深めてもらいたいと思います。
<今回の茶道文化体験でサポートしてくれた学生の声>
・私が伝えたことを真剣に聴いてくれ、しっかりとやってくれたので、みんな上手にお茶を点てることができました!
(国際観光学科4年 宮本 裕理佳さん)
・初めての着付けで、みんな戸惑っていましたが、浴衣や袴を格好良く着ることができて、喜んでくれたので、良かったです!自分にとっても着付けの勉強になりました。
(国際観光学科4年 在津 英晟さん)
・うまく伝えることができたか分かりませんが、綺麗に着付けが出来ていて良かったです。みんなが嬉しそうだったので、私も嬉しくなりました!
(国際観光学科3年 髙田 理香子さん)
2015年11月04日
高校生夏休み薬学茶道体験
日 時:2015年8月7日(金)12:40~14:00
場 所:長崎国際大学 茶室「自明堂」
主 旨:薬学部が地域貢献の一環として開催している行事で、今年で4回目となります。長崎・佐賀両県の高校生を対象としており、夏休みの期間に高校では体験できない実験等を行い、自然科学や薬学に興味を深めてもらうことが目的となっています。この薬学の研究体験のプログラムの一つとして茶道体験が組み込まれており、本学のホスピタリティ精神に触れ、茶道の魅力について感じてもらいたいと思います。
参加者:長崎・佐賀県下の高校生26名(茶道体験サポート学生7名)
1.茶席に入るために礼儀作法
武家茶である鎮信流独特の作法について講義を受け、立礼の「会釈・敬礼・最敬礼」と座礼の「爪甲礼・双手礼」を実践しました。


初めてとは思えないぐらい綺麗な双手礼でした。本学の教職員、学生も感動していました。
2.お茶の飲み方とお菓子の取り方
ここでは、本学で茶道文化の授業を履修している学生にもサポートをしてもらいました。
授業で得た知識をしっかりと高校生に伝えようと、積極的にコミュニケーションをはかっていました。この頃になると高校生も緊張がとれ、大学生との交流を楽しんでいました。


さて、お菓子の取り方では、相客のことを考え「お先に」と声をかけてからお菓子を取ります。
お茶の飲み方では、武家茶である鎮信流の作法に沿ってお茶碗を回さない飲み方を学んでもらいました。「茶碗を回すのでは?」と思っていた高校生は驚いていました。
3.はじめての茶席体験
前半に学んだ作法を活かして席入りをし、お菓子を取り回しました。
茶席では本学の学生が亭主と半東を務め、高校生をもてなしました。

初めて見るお点前に興味深々の高校生。
高校生は、美味しそうにお茶とお菓子をいただいていました。
わずかな時間ではありましたが、茶道体験を通して「おもてなしの心」を感じてもらえたのではないでしょうか。
ぜひ、茶道だけでなく様々な日本文化にも興味を深めてもらいたいと思います。
2014年08月11日
正午の茶事
皆さん、こんにちは。
今回は茶道文化Ⅳを履修する学生のお茶会、正午の茶事について紹介します。
茶道文化Ⅳの茶会は7月26日(土)に行われました。
・寄付きの様子
本学の学生とお客様の対面の様子です。
今回のお客様は学外からホテルオークラの松本様と桑田様におこし頂きました。
正客と末客は学生が務めます。着物姿の学生はいつもと違って凛々しく感じます。
・料理班の様子
盛り付けの様子です。慎重に盛り付けている緊張感が学生の表情から伝わってきますね。
・懐石料理と炭点前の様子
学生が盛り付けた料理は、いかがですか?
皆、笑顔でこちらまで楽しくなってきますね。どんな事を話しているのでしょうか?
亭主は炭点前を披露します。お客様は炭の拝見をします。
上手に炭を起こす事は出来たのでしょうか?
この後、薄茶と濃茶のお点前になります。
・集合写真
集合写真をとりお茶会の締めくくりです。
素敵な思い出がまた一つ出来た瞬間ですね。
今回は寄付きから炭点前までのご紹介でした。次のお茶会ではどんな出会いが待っているのか、次回のお茶会もご期待ください。
2014年03月07日
茶道文化ⅣB 卒業茶会を終えて
皆さんこんにちは。
今回は茶道文化を4年間履修した学生の集大成である卒業茶会について、茶会を終えた学生達の感想を混じえながらご紹介していきたいと思います。
卒業茶会は茶道文化Ⅳを履修する学生がお客様を招く、最後のお茶会になります。場所は耳順亭のお茶室で行われました。
茶会前日には、みんなで茶室と庭の掃除をして、お客様を気持ちよく迎えられるよう、準備にも余念がありません。
その甲斐あってか、当日の朝の耳順亭の空気は澄んでいてとても清々しく感じられました。
お客様が揃ったところでお茶会が始まります。
こちらは寄付きでの一場面です。
この写真は、末客がぐい飲みにお湯を注いでいる所です。夏には硝子製のぐい飲みを使用しましたが、冬場は温かみのある陶器を使用しています。このように、茶席の中では季節を表現したものが数多く存在します。
例えば、2月2日に行われた茶会で使用した香合、菓子器、主菓子は以下の通りです。
香合は鬼、菓子器はお福、主菓子は豆マスです。これらから何を連想しますか?「節分」ですね。
節分とは、本来季節が移り変わる節目を意味し、「立春」「立夏」「立秋」「立冬」それぞれの前日を指していました。ところが、日本では冬から春になる時期を一年の始まりとして考え、特に尊ばれたため、現在では立春の前日のみを節分と呼ぶようになったそうです。
最後に四年間茶道文化を履修した学生のコメントをご紹介したいと思います。
古川班の学生・・・初めは何も分からなかったけど、一つ一つ学んでいく中で、少しずつ茶道の事を理解 できたので、続けることは大切だと思いました。お茶を通して、私の人格形成に、とてもすばらしいものを得ました。
大山班の学生・・・最初は軽い気持ちで始めた茶道でしたが、4年間続けて先生方に良くしてもらい、いい 仲間にも出会うことができ毎回の授業が楽しかったです。茶道での経験を活かし、社会人になっても頑張っていこうと思います。
瓜生班の学生・・・茶道は自分と向き合える時間が増え、とてもやりがいを感じました。本格的なお茶会も 経験でき、茶道を通して礼儀作法やチームワークを身に付けることが出来たので、とても充実した4年間を過ごせたと思います。
龍・髙木班の学生・・・1年目はお点前を覚えることだけに必死になっていたので、周囲への気配りや協調 性が身についていない状態でした。ですが、2年、3年と経って行くにつれて、お点前だけでなく、茶道文化全体の雰囲気や流れを楽しめるようになっていき、少しずつですが気配りや協調性も身についてきたと思います。茶会を皆でやりとげることが出来、茶道を4年間履修して本当に良かったと思いました。