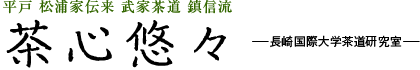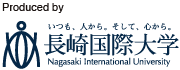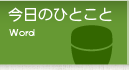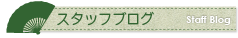2013年09月17日
第4回 茶道文化Ⅳ 正午の茶会
第4回目 正午の茶会レポートをお届けいたします!
今回は懐石料理に迫ってみましょう。どんな料理が待っているか楽しみです。
まずは、こちらの懐石膳!!
汁椀に入っている麩の色が緑に淡い黄色がまじっている様は、秋の訪れを感じさせ、まさに目で楽しむことができますね。
次はこちら!

こちらの学生さん上手にお運びしていますが気になる中身は・・・
とっても美味しそうです。竹のような飾り付けがしてありますね。そしてお豆のアクセントもあり目をひきます。
続いて一気にご紹介します。
焼き物に強肴・・・う~ん、どれも美味しそう!
ここで襖をしめ、亭主たちも昼食をとります。その間、襖の中をこっそり拝見。
なんだか楽しそう、懐石の話で盛り上がっていたらいいな。
そして、最後に・・・!!
八寸と湯桶・香の物です。最後までとっても美味しそうでした。
次回の第5回は前期最後のお茶会です。次も目が離せませんよ~!
それでは、第5回のレポートも乞うご期待!!!
2013年09月14日
第3回 茶道文化Ⅳ 正午の茶会
第3回目 正午の茶会のレポートをします!
今回の学生のメンバーは、栄養学科8名、観光学科留学生1名です。
こちらは、事前に茶会で使用する道具について嶋内教授から道具の説明があっている様子です。
学生達はメモを取りながら実際に使用する道具の知識を深めます。
今回の学生メンバーがほとんど女性であり、お客様も女性の方ということで、道具も歴史的なものを主にせず、きれいなイメージの道具を選んでいます。
茶会は、その茶会ごとにテーマを決め、そのテーマに沿った道具をそろえます。
そして、茶会当日・・・
今回の見どころは、栄養学科の学生手作りの主菓子です!
ちゃんと試作も作り、味や見た目を確かめて、本番でお客様にお出ししました。
お客様もとても喜ばれていました!
2013年09月14日
第2回 茶道文化Ⅳ 正午の茶会
茶道文化Ⅳ 第2回目、正午の茶会のレポートをしたいと思います!
8月2日、夏真っ盛りの中でのお茶会。今回お客様にお出ししたお菓子です。

干菓子:金魚と流水
主菓子:ほおずき
ほおずきは、お盆にほおずきの実を提灯に見立てて飾り、先祖を迎えるといいますね。
懐石料理にも夏の野菜が使われています。
こちらは濃茶席の様子です。水指の水が、透けているのが見えますか?
流れる水を見て涼しいと感じる、夏の風鈴の音を聞いて涼しさを感じる。このような感性は、日本人独特の感性であり文化だと思います。
その感性に響くよう、道具や料理などで季節を表現し、お客様をもてなしているのですね。
2013年09月13日
補助員研修会3日目
さて、研修会が始まって今日は3日目になります。
毎日欠かさず出席し努力を続けている補助員は、きっといい指導者になるでしょう。
今日は拝見物の出し方と中風炉点前の確認をしました。
責任ある指導者になるため、悪戦苦闘しながらもみんなメモを取るのは欠かしません。
しっかり教えたい!その熱意が伝わってきます。
とりあえず、今週はここまで。
週末、メモをもとに頭の中を整理して、また来週も頑張りましょう!
2013年09月12日